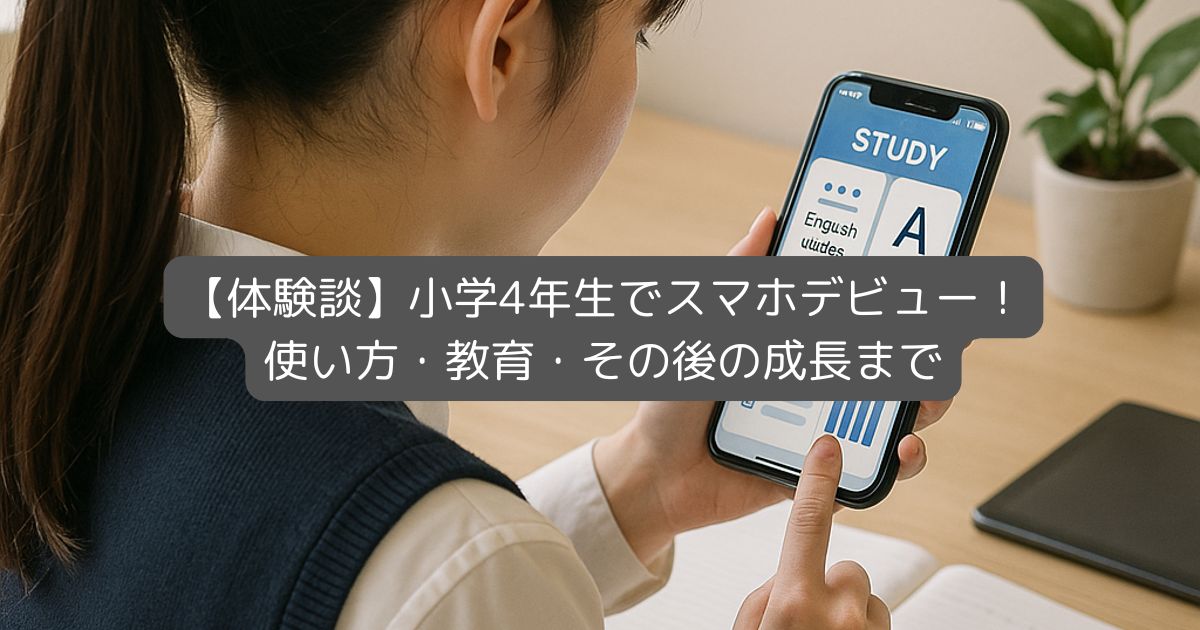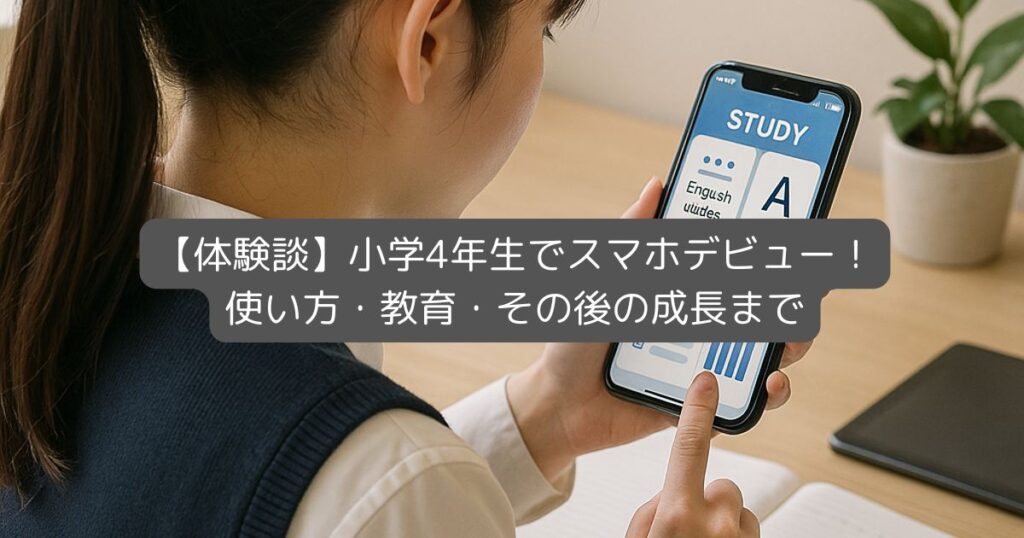
「そろそろスマホを…」迷っている親御さんへ
「うちの子、スマホが欲しいって言ってるけど、まだ早いかな?」
この記事を読んでくださっているあなたも、同じように悩まれているのかもしれません。
私もまったく同じでした。
でも今振り返ってみると、小学4年生で持たせてよかったと思えることがたくさんあります。
今回は、
我が家のスマホデビューのタイミング・使い方・家庭での教育方針、そして高校生になった今、実感している「よかった点」までをリアルにお伝えします。
今、悩んでいる皆さんの参考になれば嬉しいです。
小学4年生でスマホデビューの理由は「連絡手段」。そして「たった2つの約束」
初めてスマホを持たせたのは、小学4年生のとき。
きっかけは、習い事の終了時間が日によって違い、連絡が取りにくくなったことでした。
「単なる連絡用ツール」としてのスタートです。
でも実際には、子どもが急に遊びに行ったり、約束の時間に帰って来なかったりすることも多く、
「どこにいるのか分からない」という不安を解消してくれたことが、何よりの安心でした。
当初のルールはとてもシンプル。
- 使っていいのは家族との連絡のみ
- 使用場所は親の目の届くところ
こうした“最低限の約束”を決めてから渡しました。
もちろん、すべてが順調にいったわけではありません。
親のいないところで使ってしまったこともありましたが、そのたびに頭ごなしに叱るのではなく、冷静に話を聞くことを大切にしました。
「何をしていたの?」と尋ね、
「それならリビングでもできるよね」と、自然な流れで再度ルールを確認。
もし約束を何度も破るようであれば、
一時的にスマホの使用をストップし、一緒に考え直す時間をつくるようにしました。
こうして、少しずつスマホを安全に、適切に使う力を育てていったのです。
スマホを持たせる=「スマホ教育」のスタート
スマホはただ渡すだけではなく、どう使わせるかがすべてです。
我が家では、持たせた瞬間から「スマホ教育」をスタートしました。
💬 SNSの危険性は、早いうちから少しずつ話す
- 「ネットには優しい人ばかりじゃないよ」
- 「言葉って、読み手によってはちがって伝わることもあるんだよ」
- 「知らない人に、自分のことを教えないってすごく大事だよ」
脅かすのではなく、子どもが理解できる言葉で、怖さとマナーを伝えていくことを意識しました。
アプリを入れる前には、
- 「何ができるアプリなの?」
- 「このアプリは知らない人とつながることがあるの?」
そんな会話を必ず挟むようにしました。
もちろん制限をかけるので、知らない人とはつながることができないのですが、子供に問いかけて考えてもらうことは大事だと思います。
📱 便利な使い方は“親子で共有”
スマホは「危ないもの」ではなく、使い方しだいで学びにもなります。
我が家では、親子で一緒に使いながら、こんなことを自然と共有してきました。
- 電車の乗り換えアプリでのルート検索
- 勉強系YouTubeの調べ方とその役立て方
- 写真・動画の編集(ショート動画づくりなど)
- Googleマップでの位置確認や周辺検索
「大人がどう使っているか」を見せることで、必要な情報を探して、正しく理解して活かす力やたくさんある情報の中から、正しいものを選び取る力を少しずつ身につけていけたように思います。
高校生になって感じた「持たせてよかった」2つの成長
月日が流れ、わが子は高校生になりました。
スマホ歴もだいぶ長くなりましたが、その中で感じる「よかった」と思えることが、特に2つあります。
✅ 自分で“必要な情報”を探すのが上手になった
宿題の解き方、進路の調べ方、電車の遅延情報…
「自分に必要な情報を、自分で探して選ぶ力」が自然と育ちました。
スマホで調べることで時短になり、部活などで忙し時でも時間を有効活用できています。
最近では、旅行に出かけるときにルートを調べてくれたり、近くのおすすめカフェを見つけてくれたりもします。
✅ 他人とつながる時に“フィルター”を持っている
SNSなどで新しい友達とつながる機会も増えています。
でも小さいころから「どういう人に気をつけるべきか」を話してきたからこそ、
- 「この人、ちょっと変かも」
- 「これは言わないほうがいいな」
と、自分で考えて動けるようになりました。
やり取りの内容や投稿内容、普段の話の流れを見て、
「信頼できる人かどうか」を自分で判断している様子があります。
スマホ=危険なもの?ではなく「育てていくもの」
スマホには確かに危険もあります。
でもそれは、大人だって同じこと。だからこそ、親子で一緒に学んでいく姿勢が大切だと思っています。
- ルールを決める
- 使い方を共有する
- 困った時に話せる関係をつくる
そうすることで、スマホは「怖いもの」ではなく、子どもの可能性をひろげるツールになると私は感じています。
まとめ:スマホは“持たせるか”ではなく“どう使わせるか”
スマホを持たせるタイミングに正解はありません。
でも、「親子で一緒に学びながら使う」スタイルは、どの家庭にも取り入れられます。
うちの子も、最初は通話とメッセージだけだったのに、今では地図アプリを使って一人で目的地に行き、動画を編集し、必要な情報を正しく選べるようになりました。
スマホが、
「便利で、楽しくて、ちょっと気をつけるべきもの」
として使いこなせるようになれば、それは将来の大きな武器になります。
💡 最後にひとこと
「スマホ、まだ早いかな…?」と悩む方へ。
今まで中学生になって、初めてスマホを持ち始めた子どもたちを何人か見てきました。
周りの子は、小学生のころからスマホを使っていたので、
「これはしていい」「これはダメ」というルールや、
自分なりの時間の使い方を自然と身につけていました。
でも、中学からスマホデビューした子は、
どうしても楽しさが先に立ってしまい、
友達に合わせてスマホを使いすぎてしまうことがあったんです。
だからこそ、
周りがまだ自由にスマホを使っていないうちに、
「自分なりの使い方」「守るべきルール」をきちんと作っておくことが、とても大切だなと感じています。
親子でしっかり話し合って、安心できるスマホデビューを迎えられますよう願っています。