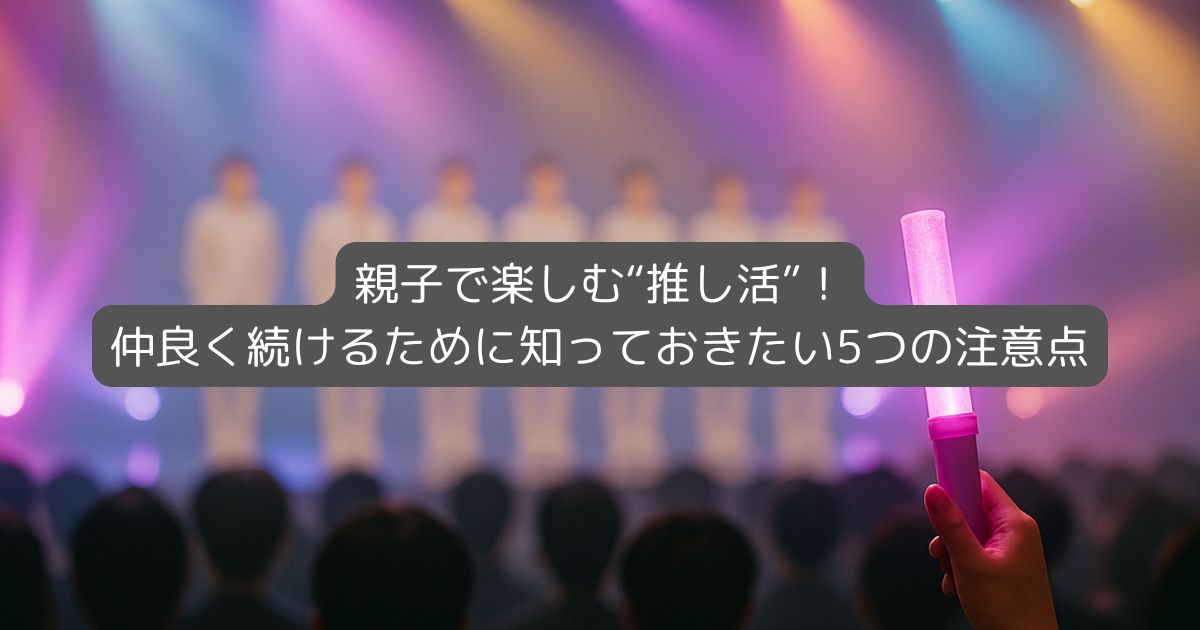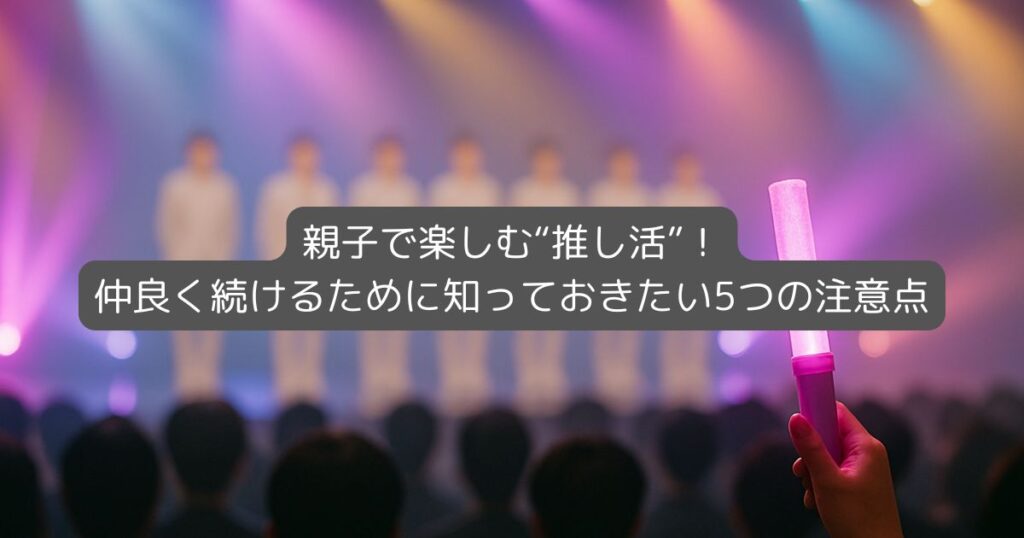
親子で楽しく、そして長く続けるために――
今回は、親子の推し活で気をつけたい5つのポイントをご紹介します。
親子で“推し活”を楽しんでいるご家庭、実は増えています。
ライブやイベントに一緒に行ったり、グッズを並べて語り合ったり。共通の趣味があると、親子の会話も自然と増えますよね。
わが家でも、娘と一緒に“推し”を応援するようになってから、会話が増え、以前より心の距離がぐっと近づいたように感じます。けれど、その一方で「ちょっと温度差あるかも?」「使いすぎてないかな…」なんて気になる瞬間も。
「親子だからこそ起こりやすいすれ違い」。
楽しく長く続けるためには、ちょっとした注意点を押さえておくことが大切です。
1. 親がハマりすぎないようにしよう
子どもと一緒に推し活をしていると、「気づいたら自分の方が夢中になっていた…」なんてこともあります。
もちろん、推しを全力で応援する気持ちは素敵なこと。でも、子どもが置いてけぼりになってしまっては本末転倒です。
「一緒に楽しもう」と始めた推し活が、いつの間にか「親が中心」になってしまうと、子どもはちょっと引いてしまうこともあります。
大切なのは、子どもの気持ちを見ながら、“一緒に楽しむ”スタンスを保つこと。
親が主導しすぎず、あくまで「子どもの世界に寄り添う」ことを意識してみてくださいね。
2.金銭感覚はしっかり共有しておこう
推し活は、意外と出費がかさむもの。
グッズ・CD・ライブ・交通費など、ひとつひとつは小さくても積み重なると大きな金額に。
親子でお金の使い方について話し合っておくことはとても大切です。
「月いくらまで」「これは自分のお小遣いから」など、あらかじめルールを決めておけば、トラブルも防げます。
そしてこれは、子どもに“金銭感覚”を伝える良いきっかけにもなります。
「欲しいものがあるとき、どうやって優先順位を決めるか」「どのくらい貯めれば手が届くか」など、実際の経験を通して学べることがたくさんあります。
また、親自身の“お金の使い方”も、子どもに大きな影響を与えます。
つい「お金はあるから」と遠征にどんどん連れて行ったり、欲しがるグッズを全部買い与えてしまったりすると、子どもは「欲しいものは簡単に手に入る」と思ってしまいがちです。
子どもの前でこそ、「これは本当に必要?」「今回は見送ろうか」などと判断する姿勢を見せることが、お金の大切さを伝える何よりの教育になります。
3.SNSでの発信は親子でルールを決めて
推し活といえば、SNSとのつながりも無視できません。今や推し活とSNSはセットのようなもの。
ライブの感想やグッズの紹介、撮った写真を投稿して、同じ“推し”のファンとつながることも楽しみのひとつです。
でも、親子でSNSを利用するなら、発信前に気をつけるべきことがいくつかあります。
特に子ども自身が気をつけておくべきポイントも多いため、一緒に話し合ってルールを決めることがとても大切です。
✅ 親が気をつけたいこと
まず、親として意識したいのが子どものプライバシーを守ること。
何気なく投稿した写真や動画に、子どもの顔や制服、学校名、家の周りの風景などが映り込んでいないか、しっかり確認しましょう。
また、「楽しかったから記録に残したい」と思って投稿したものでも、子どもが“恥ずかしい”と感じることもあるという視点は忘れずに。
「投稿してもいい?」の一言確認を習慣にしましょう。
✅ 子どもが気をつけたいこと
SNSは楽しく便利なツールですが、一度投稿した内容は完全には消せないということを、子ども自身が理解しておくことが大前提です。
「ちょっとふざけただけ」「誰にも見られないと思った」――その油断が、知らないうちに友達とのトラブルや、いじめのきっかけになることもあります。
とくに気をつけたいのが以下のポイント:
- 写真や動画を投稿するときは、背景や服装にも注意する
- 本名・年齢・住んでいる地域などは出さない
- 誰かをからかったり、見下したような内容は絶対に投稿しない
- “バズりたい”気持ちが強くなりすぎないようにする
また、他のファンの発言に傷ついたり、比べて落ち込んだりすることもあるかもしれません。
そんなときは、SNSから少し離れる勇気を持つことも大事です。
✅ 家庭で決めておきたい「SNSのルール」
親と子ども、どちらも安心して推し活が楽しめるように、家庭内でルールを決めておくのがおすすめです。
たとえば…
- 投稿は親子で一緒に内容を確認する
- 顔や本名、学校名などは出さない
- 子どもは投稿ではなく“見る専”にする
- フォロー・フォロワーは誰なのか確認しておく
- 困ったことがあれば、すぐに親に相談する
こうしたルールは、一度決めたら終わりではなく、子どもの成長に合わせて定期的に見直していくことがポイントです。
投稿は“楽しい思い出”の共有であって、無理に「バズらせる」必要はありません。
安心・安全が第一です。
4. 学校や友人関係にも配慮しよう
親子で盛り上がっていても、周囲からは「ちょっと浮いてるかも…?」と思われることもあります。
特に子どもにとって、学校での人間関係はとても大切。
「親が張り切りすぎてる」と思われたり、SNS投稿が原因でからかわれる…ということも。
推し活はあくまで家庭の中の楽しみ。
子どもが「これくらいがちょうどいい」と感じるバランスを大切にしてあげてくださいね。
5.無理なく、長く楽しめるスタイルを見つけよう
推し活は本来、「楽しい」ことがいちばん。
でも、気づかないうちに「ライブに行かなきゃ」「グッズを全部そろえなきゃ」「みんながやってるからSNSに投稿しなきゃ」と、義務感に変わってしまうことがあります。
とくに親子で推し活をしていると、どちらかが頑張りすぎて疲れてしまったり、どこかで負担になっていることに気づけなかったりするものです。
✅ 「全部じゃなくていい」が合言葉
推し活には、いろいろな形があります。
・現地のライブに行く
・配信で観る
・CDやグッズを買う
・SNSで感想を語る
・推しの写真を飾る
・静かに応援する
どれも立派な推し活であり、全部をやらなければいけないわけではありません。
「今回は配信で観ようね」「グッズはお気に入りのものだけにしようか」など、無理のない範囲を親子で話し合って決めていきましょう。
✅ 親子で“わが家流”をつくろう
家庭ごとに価値観や生活スタイルは違います。
だからこそ、「わが家はこう楽しむ」というルールをつくると、推し活がもっと気楽に、もっと続けやすくなります。
たとえば――
- ライブは年に1回行けたらOK
- グッズは予算を決めて、優先順位を話し合って選ぶ
- 推しカフェやコラボイベントは、行けるときだけ
- 忙しい時期は「追いきれなくても大丈夫」と声をかけ合う
このように、“参加しない自由”もお互いに認めておくことが長く楽しむ秘訣です。
✅ 子どもにも「バランス感覚」を
子どもにとって推し活は、楽しさが先行しがち。
でも、学校生活や習い事、体調などとのバランスを取ることも学んでいってほしいポイントです。
「今週はテストがあるから動画は週末に」「ライブの翌日は早めに寝ようね」など、【スケジュールの整え方や“切り替えの力”】も、親がサポートしていけると安心です。
また、「疲れてきたかも」「前より楽しめなくなってきた」と感じたときは、いったんお休みするのもOK。
推し活は義務ではなく、“自分の気持ちを満たすための時間”であることを、子どもにも伝えていけるといいですね。
まとめ:推し活で親子の絆をもっと深めよう
推し活は、“好きなものを一緒に楽しむ”という、とてもシンプルで温かい時間です。
ちょっとした工夫と心配りで、もっと素敵な親子の思い出になります。
注意点を押さえつつ、推しとの時間、そして親子の時間を大切にしていきましょう!